*この記事は、アフィリエイト広告を利用しています。
災害に備える、「自宅備蓄」の作り方と設置場所【防災対策】

防災備蓄していますか?近年では、日本国内で色々な防災対策が国をあげて行われている印象を受けています。
例えば、電車のTVなどでも防災の取り組みを意識したCMや、BCP(事業継続計画)を早急に進めている業界や企業もあります。
ブログ運営者のポチ(@sunrise_033)です。
しかしながら、個人や家族単位になると自分たちが備えをして身を守る、家族を守る取り組みがもっとも大切であり効果があるのは伺いの余地はありませんよね。
この記事では「自宅備蓄の手順」と「中身の一覧」を紹介していきます。この記事を読めば、「自宅備蓄の事前準備」が一目でわかるように解説しています。
ぜひ、個人の家族の防災対策として参考になれば幸いです。

- お得に暮らし、コツコツ副収入で心豊かに。あなたをそっと応援するブログを運営
- お得な節約、コツコツ投資、ブログ収益化の3つが主軸コンセプト
- 月間54,000PV/収益5桁達成中
- フード・グルメブログも別サイトで運営中
自宅備蓄の手順一覧
自宅備蓄の手順は下記になります。
- 自宅備蓄のスペースを確保する
- 食料備蓄を用意する
- ライフライン確保の備蓄を用意
この流れで準備します。(手順1)は「スペースの確保」、(手順2〜3)は備蓄の中身を説明しています。
下に一覧リストをのせていきますので参考にどうぞ。
| リスト | 備考 |
| 手順1:自宅備蓄のスペースを確保する | |
| クリアケース | 大きめで中が見えるもの |
| 置き場所 | 玄関・リビングなど |
| 手順2:食料備蓄を用意する | |
| 飲料水:1人1日3リットル目安、3日分(家族分は×人数分) | |
| 水(1人1日3ℓ) | 2ℓペット 6本 |
| 食料:1人1日3食が目安、3日分(家族分は×人数分) | |
| 米・無洗米 | 1食0.5合の計算、1kg(13食分) |
| 缶詰(魚などタンパク源) | 4缶 |
| 缶詰(果物) | 2缶 |
| 準備しておくと安心な食べ物 | |
| レトルト食品 | 簡単に食べられる |
| 乾麺(そば・そうめん | 主食で保存も効く |
| 即席麺・カップ麺 | お湯を注ぐだけ |
| 乾パン | 保存が効く |
| シリアル | 栄養価が高い |
| ロングライフ牛乳 | 3ヶ月程度保存可能 |
| 梅干し | 塩分補給、殺菌作用 |
| チョコレートなど甘味 | ストレス緩和 |
| 手順3:ライフライン確保の備蓄を用意 | |
| カスコンロ | 1台、ガスが一番復帰まで長い |
| ボンベ | 1台に4本 |
| 懐中電灯 | 一番役に立つアイテム |
| LEDランタン | 広範囲を照らせるので、あると便利 |
| モバイルバッテリー | 電気の復旧に数日かかるので、その間をしのぐ必須ツール |
| USBケーブル | 予備があると、便利 |
| スリッパ | ないと歩けません。必須 |
| 乾電池の予備 | 懐中電灯、ラジオに使用、必須 |
| 水タンク (バケツで代用可能) | 水道使えるまでの水(生活用水)の確保に使用 |
| 非常用トイレ | 水道使えるまでの数日〜一週間くらいの備蓄が必須 |
手順1:自宅備蓄のスペースを確保する
初めに事前準備といて備蓄するスペースを確保します。
僕の場合は収納スペースがないので、寝室にクリアケースを置いて備蓄スペースを確保しました。

(幅39cm×奥行68cm×高さ30cm)
スーパーの収納コーナーで購入しました。(700円くらい)
蓋がしっかり固定できるので転倒によって備蓄が散らかるリスクを軽減でき、クリアケースなので外見で何が入っているのかわかりやすいものを選びました。
備蓄グッズの置き場所は?
- 取り出しやすい
- 避難経路の導線
クローゼットの中や床下収納におくよりも、玄関やリビング、ワンルームなら出入り口に近くですぐ取り出せる場所に置くのが良いです。
- クローゼットの中
- 床下収納
自宅がめちゃめちゃになってしまった時に部屋の奥のクローゼットの下に入っているとしたら取り出すことが大変ですね。
-150x150.png) ポチ
ポチ比較的出入り口(避難経路)に近い場所に設置しておきましょう。
手順2:食料備蓄を用意する
食料や飲み水は電気・ガス・ライフラインが止まった時にとても必要になっていきます。なので日頃から備えていくのが良いです。
災害時は冷蔵庫の中身から食べていき、備蓄分はそのあとに食べていきます。
- 飲料水:1日3リットル目安で3日分
- 食料:3日分(保存の効くもの)
大規模になると約1週間分の備えが必要だとされています。
食料備蓄の基本は「炭水化物+タンパク質」の組みあわせが良いとされています。
最低限必要な食料備蓄リスト
| 最低限必要なもの(1人あたり) | 数 |
|---|---|
| 水(1人1日3ℓ) | 2ℓペット 6本 |
| 米・無洗米 ・アルファ米 (1食0.5合の計算) | 1kg(13食分) |
| 缶詰(魚などタンパク源) *缶切り不要もの | 4缶 |
| 缶詰(果物) *缶切り不要もの | 2缶 |
できれば準備したい食料備蓄リスト
| 準備しておくと安心 | 備考 |
|---|---|
| レトルト食品 | 簡単に食べられる |
| 乾麺(そば・そうめん | 主食で保存も効く |
| 即席麺・カップ麺 | お湯を注ぐだけ |
| 乾パン | 保存が効くうえ、加熱や水を使わない |
| シリアル | 栄養価が高い |
| ロングライフ牛乳 | 温保存で未開封なら3ヶ月程度保存可能 |
| 梅干し | 塩分補給、殺菌作用、疲労回復 |
| チョコレートなど甘味 | ストレス緩和、 エネルギー補充 |
参考元:緊急時に備えた家庭用食料品備蓄ガイド:農林水産省
*農林水産省ページ内の「緊急時に備えた家庭用食品備蓄ガイド」から
手順3:ライフライン確保の備蓄を用意
食料以外でも備蓄しておきたいのが、電気やガスが使えなくなった時のことを想定した備蓄リストです。
- カスコンロ・ボンベ
- 懐中電灯・LEDランタン
- 充電器(モバイルバッテリー)
- USBケーブル
- スリッパ・内履き用の靴
- 乾電池の予備
- 水タンク
- 非常用トイレ
カスコンロとボンベ
ガスボンベの備蓄数はガスコンロ 1台あたり4本が目安です。
ガスが止まった時に調理の熱源を確保します。実は電気よりも復旧に時間がかかるのがガスと水なんです。
ガスコンロ近くのスーパーなどでも2000円しないくらいで買うことができます。
ボンベはコンビニなんかでも売ってますよ。
懐中電灯・LEDランタン

阪神・淡路大震災の避難生活で役に立った1番役に立ったアイテムが懐中電灯だそうです。
またスマホのライトなどでも代用できますが災害時はバッテリーの保存が優先されるのでこういったアイテムは必要不可欠です。

充電器(モバイルバッテリー)

スマホを2〜3回分充電できる持ち運びできる充電器(モバイルバッテリー)を持っていれば電気が使えなくなってもスマホのバッテリーが切れる不安を軽減されます。
10000mAhでのフル充電目安
| 端末 | バッテリー量 | フル充電回数 |
|---|---|---|
| iPhone 7 | 1960mAh | 約3.2回 |
| iPhone 7plus | 2900mAh | 約2.2回 |
| iPhone 8 | 1821mAh | 約3.5回 |
| iPhone 8plus | 2691mAh | 約2.3回 |
| iPhone X | 2761mAh | 約2.3回 |
| iPhone XS | 2659mAh | 約2.4回 |
| iPhone XS max | 3179mAh | 約2.0回 |
| iPhone SE2 | 1821mAh | 約3.5回 |
| iPhone 11 | 3110mAh | 約2.0回 |
| iPhone11Pro | 3046mAh | 約2.0回 |
参考元:MOOVOO
Androidスマホの場合はバッテリー容量を調べて比較してみてください。
またガラケー(フューチャーフォン)の場合は容量が多くても1000mAhくらいと言われています。
-150x150.png) ポチ
ポチ10000mAhの充電器なら約6回分フルに充電することができますよ。

USBケーブル
充電器(モバイルバッテリー)で一緒に用意していきたいのがUSBケーブルです。
自分に必要なスマホやポケットWi-Fiなどの端末規格を調べて必要なら揃えていくと良いでしょう。
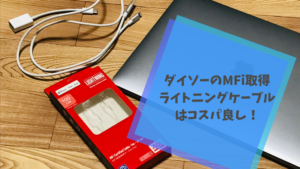
乾電池の予備
備蓄の目安は電気が復旧するまでの1週間分くらいで約50本が目安となります。
乾電池は懐中電灯やLEDランタン、ラジオ、充電器でも乾電池式のものに欠かせません。
スリッパ・内履き用の靴

地震などの災害時にはガラスの破片や瓦礫などが散乱して危険な状態もあり得ます。
災害時の怪我が病院もパンクし、行くことも困難ですので避けたいところですよね。
-150x150.png) ポチ
ポチなのでスリッパや内履き用の靴が必須になります。

水タンク
水タンクは災害時に水道が使えなくなることを想定して持っていると役に立ちます。
また水道管が使えなくなると公園などから給水しにいくほかありませんのでこの時も使います。
バケツやポリ袋などで代用もできます。
災害用トイレは必須アイテム!
出典元:amazon
人間食べれば必ず生理現象として出ますので、そういった意味でも非常用トイレの備えは必須です。
というのも、大地震などにより水道管が破損することは少なくありません。
こういう場合は水が使えなくなり飲み水や手を洗う、シャワーなどもそうですが、下水も流れません。
-150x150.png) ポチ
ポチ過去の地震などの災害を見てもトイレ問題は大きな課題となっています。
災害時は仮設トイレが設置されるが、時間がかかる
また災害が発生してからのトイレは主に仮設トイレは設置されるのですが、災害発生場所に運び入れるので大変時間がかかる作業になります。
大規模災害では、発生してから設置まで数日間かかることもあるようです。
公園や避難所で使おうとしてもそもそもその地域が断水している場合もあります。(マンションタイプだと停電により、水が組み上がらないため使えないこともあり)
-150x150.png) ポチ
ポチ水無しで使える災害用トイレは備蓄しておくと安心です。
参考元:避難所の生活環境対策 : 防災情報のページ – 内閣府
*「避難所におけるトイレ確保・管理ガイドライン(平成28年4月)PDF形式」から閲覧可能

posted with カエレバ
まとめ
この記事では「自宅備蓄の手順」と「中身の一覧」を紹介しました。
まとめると、
- 自宅備蓄のスペースを作る
- 飲食備蓄を確保
- ライフライン備蓄を確保
- 非常用トイレは特に重要
このようになります。
いざという時に迅速に行動できるのは、事前に準備があってこそです。
少しづつでも良いので、できるところから備蓄を進めていきたいですね。

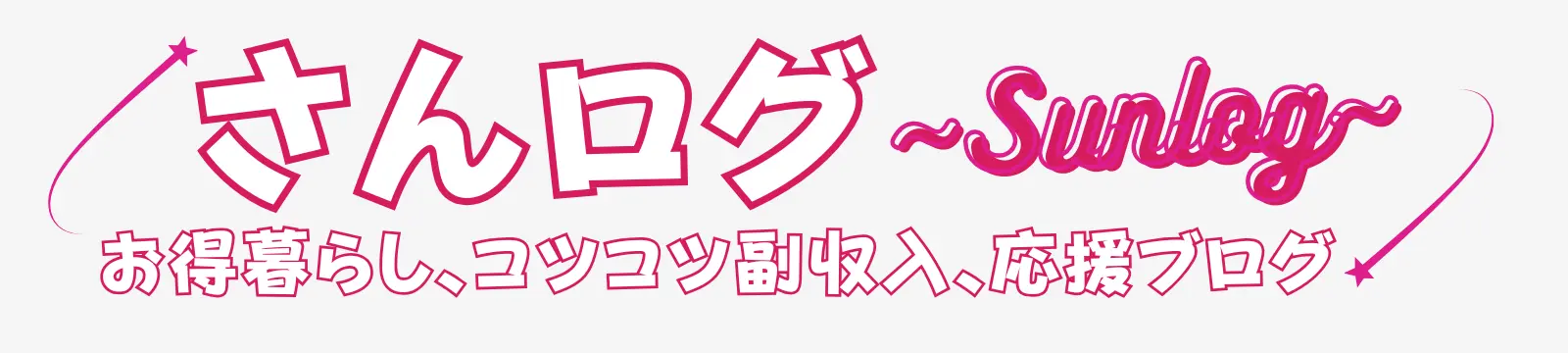



コメント